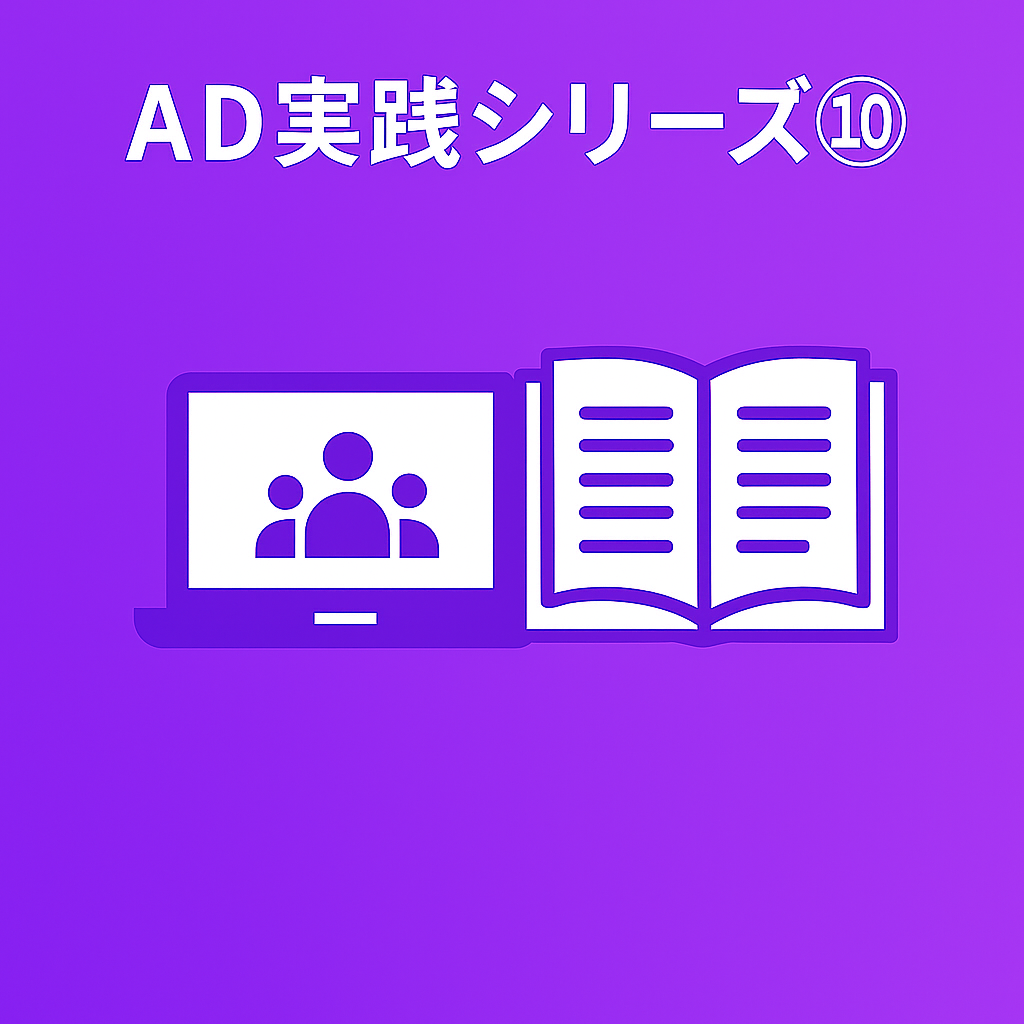本コラムは、中小企業の現場で活用されるActive Directory(AD)について、実務で役立つ知識を段階的に学べる「AD実践シリーズ」の第10回です。
ActiveDirectory(AD)は、企業の情報システムの中核を担う重要な存在です。しかし、ADの運用保守は専門的な知識が求められ、現場のIT担当者にとって負担となることも少なくありません。本記事では、AD運用保守の現場でIT担当者が押さえておくべきルールやポイントを解説し、日々の業務を円滑に進めるためのヒントを提供します。
目次
AD運用保守における基本原則
ADの役割と重要性を理解する
ActiveDirectory(AD)は、現代の企業ネットワークにおいて、 中核的な役割を担っています。ユーザーアカウントの管理、認証プロセスの実行、リソースへのアクセス制御、グループポリシーの適用など、その機能は多岐にわたります。ADが正常に機能することで、従業員は安全かつ効率的に業務を遂行できます。ADに障害が発生すると、業務が停滞するだけでなく、セキュリティリスクも高まります。例えば、ユーザーがシステムにログインできなくなったり、重要なファイルにアクセスできなくなったりする可能性があります。したがって、IT担当者はADの役割と重要性を深く理解し、常に安定稼働を心がける必要があります。そのためには、ADの基本的な概念、構成要素、および運用に関する知識を習得し、定期的なメンテナンスと監視を行うことが不可欠です。ADの重要性を認識することは、効果的な運用保守を行うための第一歩となります。
ドキュメント作成と管理の徹底
ADの運用保守において、ドキュメントの作成と管理は非常に重要な要素です。AD環境は複雑であり、構成、設定、変更履歴などを正確に記録し、ドキュメントとして管理することで、問題発生時の迅速な対応や、担当者変更時のスムーズな引継ぎが可能になります。 具体的には、ADのドメイン構造、OU(Organizational Unit)の構成、グループポリシーの設定内容、アカウント管理ポリシー、 変更履歴、障害対応手順などを詳細に記録します。これらのドキュメントは、ADの運用に関わるすべての担当者がアクセスできるように、一元的に管理することが望ましいです。例えば、共有フォルダやWiki、ドキュメント管理システムなどを活用することで、情報の共有と更新を容易にすることができます。また、ドキュメントは定期的に見直し、最新の状態に保つように心がけましょう。ドキュメントが不正確であったり、古くなっていたりすると、誤った対応を招き、システム障害を悪化させる可能性があります。
変更管理プロセスの確立
ADに対する変更は、システム全体に影響を及ぼす可能性があるため、変更管理プロセスを確立し、慎重に進める必要があります。変更管理プロセスとは、ADに対する変更要求の受付、変更内容の評価、承認、実施、および変更結果の検証と記録を含む一連の手順のことです。変更要求は、変更の目的、 変更内容、影響範囲、実施スケジュールなどを明記した申請書を提出させるのが一般的です。変更内容は、事前にテスト環境で検証し、問題がないことを確認してから本番環境に適用します。また、変更作業は、可能な限り営業時間外に行い、システムへの影響を最小限に抑えるように心がけましょう。 変更後には、必ず動作確認を行い、問題がないことを確認します。変更管理プロセスを確立することで、誤った設定変更によるシステム障害を未然に防ぎ、ADの安定稼働を維持することができます。また、変更履歴を記録することで、問題発生時の原因究明や、過去の設定状態の復元に役立ちます。
アカウント管理の徹底
アカウントポリシーの設定
アカウントポリシーは、AD環境のセキュリティを維持するために不可欠な要素です。強力なパスワードポリシーを設定し、不正アクセスを防止することが重要です。具体的には、パスワードの最小文字数、複雑さの要件(大文字、小文字、数字、記号の組み合わせ)、パスワードの有効期限、パスワードの再利用制限などを設定します。また、アカウントロックアウトポリシーを設定し、一定回数以上パスワードを間違えた場合にアカウントをロックすることで、ブルートフォースアタックによる不正アクセスを防止します。アカウントポリシーは、グループポリシーを通じてAD環境全体に適用することができます。ただし、アカウントポリシーを厳しくしすぎると、ユーザーの利便性を損なう可能性があるため、セキュリティと利便性のバランスを考慮して設定する必要があります。例えば、パスワードの有効期限を短くしすぎると、ユーザーが頻繁にパスワードを変更しなければならなくなり、パスワードを忘れたり、メモしたりする可能性が高まります。
不要なアカウントの削除
退職者や異動者のアカウントは、速やかに削除または無効化することが重要です。放置されたアカウントは、不正アクセスの温床となる可能性があります。例えば、退職した従業員のアカウントが残っている場合、そのアカウントが悪意のある第三者に乗っ取られ、機密情報が漏洩したり、システムが破壊されたりする可能性があります。アカウントの削除または無効化は、組織の退職・異動プロセスと連携して行うことが望ましいです。例えば、人事部門から退職・異動者の情報がIT部門に通知され、IT部門がアカウントの削除または無効化を行うという流れを確立します。また、アカウントの棚卸しを定期的に行い、不要なアカウントがないか確認することも重要です。アカウントの棚卸しとは、AD環境に存在するすべてのアカウントを洗い出し、それぞれのアカウントが現在も必要かどうかを確認する作業のことです。アカウントの棚卸しを行うことで、不要なアカウントを特定し、削除または無効化することができます。
特権アカウントの管理
ドメイン管理者などの特権アカウントは、AD環境全体に対する強力な権限を持つため、厳重に管理する必要があります。特権アカウントは、必要最小限のユーザーにのみ付与し、共有アカウントの使用は避けるべきです。 共有アカウントとは、複数人で同じアカウントを共有して使用するアカウントのことです。共有アカウントを使用すると、誰がどのような操作を行ったのかを特定することが困難になり、セキュリティリスクが高まります。特権アカウントのパスワードは、定期的に変更し、複雑で推測されにくいものを設定します。また、特権アカウントの利用状況を監視し、不審なアクティビティがないか確認することも重要です。特権アカウントの利用状況の監視には、特権アクセス管理(PAM)ツールを使用するのが一般的です。 PAMツールは、 特権アカウントの利用を制御し、監査ログを記録することで、セキュリティを強化します。さらに、多要素認証(MFA)を導入することで、特権アカウントのセキュリティをさらに向上させることができます。
セキュリティ対策の実施
定期的なセキュリティ監査
AD環境のセキュリティ設定に不備がないか、定期的に監査を実施することが重要です。セキュリティ監査とは、AD環境のセキュリティに関する様々な項目をチェックし、脆弱性やリスクを特定する作業のことです。セキュリティ監査の対象となる項目としては、アカウントポリシーの設定、グループポリシーの設定、アクセス許可の設定、イベントログの設定、ソフトウェアのバージョンなどが挙げられます。セキュリティ監査は、専門のセキュリティ監査ツールを使用するか、手動でチェックリストに基づいて行うことができます。セキュリティ監査の結果に基づいて、脆弱性やリスクを修正し、セキュリティレベルを向上させます。 セキュリティ監査は、定期的に(例えば、四半期ごとや年ごと)実施し、継続的にセキュリティレベルを維持することが重要です。また、セキュリティ監査の結果は、ドキュメントとして記録し、今後のセキュリティ対策の参考にします。セキュリティ監査を定期的に実施することで、AD環境のセキュリティリスクを早期に発見し、適切な対策を講じることができます。
マルウェア対策
ADサーバーに対するマルウェア対策ソフトの導入は必須です。ADサーバーは、AD環境の中核となる重要なサーバーであり、マルウェアに感染すると、AD環境全体に影響が及ぶ可能性があります。マルウェア対策ソフトは、リアルタイムスキャン機能、定期スキャン機能、および自動アップデート機能を備えたものを選択します。リアルタイムスキャン機能は、ファイルが作成、変更、またはアクセスされた際に、マルウェアを検出し、駆除する機能です。定期スキャン機能は、定期的にADサーバー全体をスキャンし、マルウェアを検出、駆除する機能です。自動アップデート機能は、マルウェア定義ファイルを常に最新の状態に保つ機能です。マルウェア定義ファイルとは、既知のマルウェアに関する情報が記述されたファイルのことです。マルウェア対策ソフトは、常に最新の状態に保つように心がけましょう。また、マルウェア対策ソフトの設定を適切に行い、ADサーバーのセキュリティを最大限に高めるようにします。
イベントログの監視
ADサーバーの イベントログを監視し、異常なアクティビティやエラーを早期に発見することが重要です。イベントログとは、ADサーバー上で発生した様々なイベント(ログオン、ログオフ、エラー、警告など)が記録されたファイルのことです。イベントログを監視することで、不正なログオン試行、アカウントロックアウト、サービス停止などの異常を早期に発見し、適切な対応を行うことができます。イベントログの監視は、手動で行うこともできますが、イベントログ監視ツールを導入することで、効率的に監視を行うことができます。イベントログ監視ツールは、イベントログをリアルタイムで監視し、異常なイベントが発生した場合にアラートを発する機能を提供します。また、イベントログ監視ツールは、イベントログを分析し、セキュリティに関するレポートを作成する機能も提供します。イベントログ監視ツールを導入することで、ADサーバーのセキュリティを強化し、システム障害を未然に防ぐことができます。
障害発生時の対応
バックアップからの復元
ADサーバーのバックアップは、定期的に実施し、障害発生時には迅速に復元できるように準備しておく必要があります。バックアップは、システム全体をバックアップするフルバックアップと、変更されたデータのみをバックアップする差分バックアップまたは増分バックアップを組み合わせて行うのが一般的です。バックアップ頻度は、システムの重要度や変更頻度に応じて決定します。例えば、重要なシステムの場合は、毎日フルバックアップを行い、差分バックアップを数時間ごとに行うのが望ましいです。バックアップデータは、ADサーバーとは別の場所に保管し、災害などによるデータ消失に備える必要があります。バックアップからの復元手順は、事前にテストしておき、障害発生時にスムーズに復元できるように準備しておきます。バックアップからの復元には、ADサーバーのオペレーティングシステム、ADデータベース、および関連する設定ファイルを復元する必要があります。バックアップからの復元作業は、慎重に行い、データの整合性を保つように注意します。
フェールオーバー環境の構築
ADサーバーに障害が発生した場合に備えて、フェールオーバー環境を構築することが望ましいです。 フェールオーバー環境とは、ADサーバーが停止した場合に、自動的に別のADサーバーに切り替わるように構成された環境のことです。フェールオーバー環境を構築することで、ADの停止時間を最小限に抑え、業務への影響を軽減することができます。フェールオーバー環境の構築には、複数のADサーバーを用意し、それらを連携させる必要があります。ADサーバー間の連携には、ADのレプリケーション機能を使用します。ADのレプリケーション機能は、ADサーバー間でデータを自動的に同期する機能です。フェールオーバー環境を構築する際には、フェールオーバーの手順を事前にテストしておき、障害発生時にスムーズに切り替えられるように準備しておきます。また、フェールオーバー環境は、定期的にメンテナンスを行い、正常に機能していることを確認する必要があります。フェールオーバー環境を構築することで、ADの可用性を高め、事業継続性を確保することができます。
障害対応手順の確立
ADサーバーに障害が発生した場合の 対応手順を確立し、ドキュメントとして管理することが重要です。障害対応手順には、障害の切り分け、原因の特定、復旧作業、および再発防止策の検討などが含まれます。 障害対応手順は、ADの運用に関わるすべての担当者が理解できるように、わかりやすく記述する必要があります。また、障害対応手順は、定期的に見直し、最新の状態に保つように心がけましょう。障害対応手順を確立することで、障害発生時に迅速かつ適切に対応することができ、システム障害による影響を最小限に抑えることができます。また、障害対応手順をドキュメントとして管理することで、担当者が変更になった場合でも、スムーズに障害対応を行うことができます。障害対応手順は、実際の障害事例に基づいて作成し、 定期的に訓練を行うことで、より実効性の高いものにすることができます。
まとめ:AD運用保守の継続的な改善
AD運用保守は、一度ルールを定めたら終わりではありません。技術の進歩やビジネス環境の変化に合わせて、 定期的に見直しを行い、改善を続けることが重要です。クラウドサービスの活用や、自動化ツールの導入などにより、運用管理の効率化やセキュリティ強化を図ることも可能です。常に最新の情報を収集し、 AD運用保守のレベルアップを目指しましょう。具体的には、ADに関する最新のセキュリティ情報、新しい機能、およびベストプラクティスなどを定期的に調査し、自社のAD環境に適用できるものがないか検討します。また、ADの運用状況を定期的に分析し、ボトルネックとなっている箇所や、改善の余地がある箇所を特定します。そして、特定された課題に対して、具体的な改善策を立案し、実行します。AD運用保守の継続的な改善は、AD環境の安定稼働を維持し、ビジネスの成長を支えるために不可欠です。
弊社では、Active Directoryの構築支援や運用保守サービスも提供しております。
「導入したいけどノウハウがない」「管理が煩雑で困っている」など、
ADに関するお悩みがございましたら、ぜひこちらよりお気軽にお問合せください。